映画『ブリキの太鼓』の概要:「ブリキの太鼓」(原題:Die Blechtrommel)は、1979年のドイツ映画。原作はドイツの作家ギュンター・グラスが1959年に発表した長篇小説。監督は「テルレスの青春」、「カタリーナ・ブルームの失われた名誉」などのフォルカー・シュレンドルフ。主演のオスカル・マツェラート役にダーフィト・ベンネント。オスカルの父・アルフレート・マツェラート役にマリオ・アドルフ。オスカルの母・アグネス・マツェラート役にアンゲラ・ヴィンクラー、フランス人シンガー・俳優のシャルル・アズナヴールなど。
映画『ブリキの太鼓』 作品情報

- 製作年:1979年
- 上映時間:142分
- ジャンル:ヒューマンドラマ
- 監督:フォルカー・シュレンドルフ
- キャスト:ダーヴィット・ベネント、マリオ・アドルフ、アンゲラ・ヴィンクラー、ハインツ・ベネント etc
映画『ブリキの太鼓』 評価
- 点数:95点/100点
- オススメ度:★★★★★
- ストーリー:★★★★★
- キャスト起用:★★★★★
- 映像技術:★★★★★
- 演出:★★★★★
- 設定:★★★★☆
[miho21]
映画『ブリキの太鼓』 あらすじ(ストーリー解説)
映画『ブリキの太鼓』のあらすじを紹介します。
1899年のダンツィヒ。カシュバイの荒れ野に4枚のスカートを穿いて座り込み、収穫した芋を焼いていたアンナ(ティーナ・エンゲル)は、逃げてきた放火魔のコリヤイチェク(ローラント・トイプナー)をスカートの中に匿い、やがてアンナは彼との間に女の子を設けた。第一次大戦が終り、その成長した娘アグネス(アンゲラ・ヴィンクラー)はドイツ人のアルフレート(マリオ・アドルフ)と結婚するが、従兄のポーランド人ヤン(ダニエル・オルブリフスキ)と愛し合い1924年にオスカルを生む。生まれた彼はすでに目が開いており、胎児の頃から意識を持っていた。
3歳になったオスカル(ダーフィト・ベンネント)は、誕生日に母からブリキの太鼓をプレゼントされるが、耐え難い大人たちの狂態に抗うように、自らの意志で階段を落ち成長を止めてしまう。この時からオスカルにはある種の超能力が備わり、彼が太鼓を叩きながら叫び声を上げるとガラスが粉々になって割れた。毎週木曜日になるとアグネスはオスカルを連れ、ユダヤ人のおもちゃ屋マルクス(シャルル・アズナヴール)の店に行く。彼女はマルクスにオスカルを預け、近くの安宿でポーランド郵便局に勤めるヤンと逢いびきを重ねていた。そんな中、ダンツィヒの街では第三帝国を成立させたヒトラーの声がラジオに響いていた。両親と共にサーカス見物に出かけたオスカルは、10歳で成長を止めたという団長のベブラ(フリッツ・ハックル)に会い、彼から小さい人間の生き方を聞いた。ヤンも含めた四人で海岸に遠出した時、引きあげられた馬の首から無数のウナギが這い出るのを見て嘔吐する母アグネス。彼女はヤンの子を宿していたが、それ以来口を聞かなくなり、狂ったように魚だけをむさぼり始め、やがて自ら命を絶ってしまう。ナチスの勢力が強まった1939年9月l日、ポーランド郵便局襲撃事件が起こりヤンは銃殺される。マツェラート家にオスカルの母親代わりとして16歳の少女マリア(カタリーナ・タールバッハ)が訪れるが、オスカルとベッドを共にしながらも、彼女はマツェラートの妻になり息子クルトを生む。クルトを我が子と信じて疑わないオスカルは、3歳になったら太鼓を贈ると約束し、再会したベブラらと共に慰問の旅へ出た。慰問団のヒロインであるロスヴィーダ(マリエラ・オリヴェリ)との幸福な日々を過ごすオスカルだったが、連合軍の襲撃による爆撃で彼女は絶命する。オスカルが故郷に帰った当日はドイツ降伏の前夜であり、クルトは3歳の誕生日を迎えていた。侵攻してきたソ連兵にマツェラートは射殺され、彼の葬儀の日にオスカルはブリキの太鼓を棺の中に投げ込み、彼は成長することを決意する。その時、オスカルはクルトが投げた石で気絶するが、祖母のアンナ(ベルタ・ドレーフス)は彼を介抱しながらカシュバイ人の生き方を語る。そして成長をはじめたオスカルはアンナに見送られ、汽事に乗ってカシュバイの野から西ヘと去って行った。

映画『ブリキの太鼓』 感想・評価・レビュー(ネタバレ)
映画『ブリキの太鼓』について、感想・レビュー・解説・考察です。※ネタバレ含む
”マトモ”を自称する人は観ない方がよい
見せ物的なサーカスの小人(コビト)は昔から映画によく使われていた表現であり、実際に小人プロレスなどというものも存在していたのだが、一種の発達障害なので健康体でありながらも最近はタブーと扱われているのか全く見かけなくなった。ドイツの映画というところで”キッチュ”という前衛的な表現で片づけてしまうか、何か深さを物語る作品なのかと二者択一に迫られれば、迷わず前者を選んでいいというニュアンスの作品である。この題材を選んだ必然性というところで考えると、余りにも奇妙で奇天烈な表現に一貫されており、確かに戦時下の物語ではあるが、ナチズムの狂気に犯された人々の苦悩を描いたものでもない。自ら成長を拒否した人間の物語ではあるが、大人の醜悪さと子供の残虐さをここまで誇張して描いた映画はそう目にかかれるものではない。いわゆる社会的な通念もなく、極めて個人的な物語であり、その周辺にまとわりつくような悲惨な生活が無情に展開して行くだけである。仮にこういった現実に対面した場合、人はどうやって対処したらよいのかという事に目を背けず、精神的な耐性を付けるには相応しい作品かも知れないが、唯々、その引きこまれる映像の力は凄まじいの一言である。
主人公オスカル役のダーフィト・ベンネント
余りにも異端な主人公のオスカル役を演じるダーフィト・ベンネントが本作の全てである。逸材であることは間違いないのだろうが、この子役は物語と同じように成長が止まっていたと言う事実の中で生きていた。それを本作のような映画の主役に抜擢したという事実には正直絶句してしまう。感情を押し殺した飄々とした演技力は子供のものとは思えない部分があり、リアル過ぎる演技の裏側にその事実があるという事を考えると、どうにも言い表せないようなもどかしささえ感じてしまう。制作者にしてみれば、この地獄絵巻にこれほど相応しい主人公はいなかったという事なのだろう。余りにもセンセーショナルな裏側にも驚くばかりだ。
映画『ブリキの太鼓』 まとめ
”異常”とか”特殊”というものが隠されず公にされていた時代背景と相俟って、戦争というこれもまた異常な背景の中で繰り広げられる狂気の沙汰を描いたストーリーだが、考えれば世界中どこにでもこのような奇異な話は転がっていたのだろう。それを物語として採り上げ逸話として仕立ててしまうにもそれほど困難な社会ではなかったのだろう。フランス文学でも似たような話は多く、人権的にも未成熟な社会でさほどタブーと見なされていなかった現実が、特殊な眼力を持つ表現者によって紡がれたものが多くの書籍に記されている。読むだけで気分の悪くなる話をこのようにう映像に残す必然性があるのかどうかはさておき、表現の自由という名の下に作られた作り話にしてもあまりにも特異な物語である。毒々しく寓意と汚辱にまみれ、デフォルメされた出演者たちが繰り広げる、極めてリアルに感じられる不可思議な世界感。怖いもの見たさという不道徳さで人を惹き付けてやまない反面、言い知れぬ無常観に襲われる魔性の物語である。


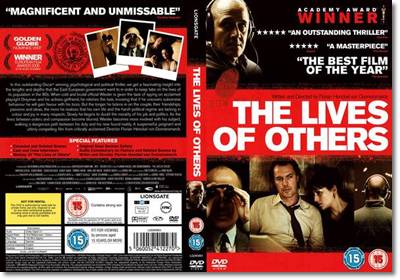
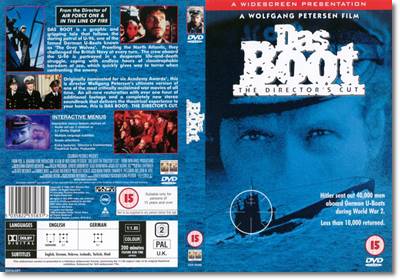
みんなの感想・レビュー
私は23才の時に日本で見ました。内容を知らないで、ただドイツの映画が好きだというだけで見たわけでしたが、こがいなキテレツなストーリーにはびっくりしてしまいました。悪魔のような子供が怖いのは確かですが、家族の大人たちも道徳心の欠片もない変わった人ばかりで、死に追いやられても仕方ないです。