この記事では、映画『陽のあたる教室』のあらすじをネタバレありの起承転結で解説しています。また、累計10,000本以上の映画を見てきた映画愛好家が、映画『陽のあたる教室』を見た人におすすめの映画5選も紹介しています。
映画『陽のあたる教室』の作品情報
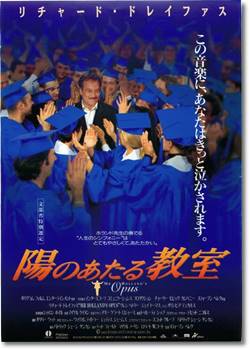
上映時間:144分
ジャンル:ヒューマンドラマ、音楽
監督:スティーヴン・ヘレク
キャスト:リチャード・ドレイファス、グレン・ヘドリー、ジェイ・トーマス、オリンピア・デュカキス etc
映画『陽のあたる教室』の登場人物(キャスト)
- グレン・ホランド(リチャード・ドレイファス)
- 主人公。ピアノマンとして、バンドで各地を回った経験を持つ。本業は作曲家だが、それだけでは食べていけないため、未経験の音楽教師の職に就く。作曲、授業、生徒の個別指導というルーチンをこなす。
- アイリス・ホランド(グレン・ヘドリー)
- ホランドの愛妻。写真家。アイリスのバイト代とホランドの教職給で生計を立てている。キュートで繊細。夫を温かく見守る。
- ビル・マイスター(ジェイ・トーマス)
- ホランドの同僚の体育教師。軍隊の出で、フットボール部の顧問を務める。独身で、自分の子どもは生徒だと思っている。ホランドの良き友人となる。
- ジェイコブ校長(オリンピア・デュカキス)
- ジョン・F・ケネディ高校の女性校長。誇り高く、優秀なキャリアウーマン。教師未経験のホランドに厳しく接しつつも理解を示す。
- ウォルターズ副校長(W.H.メイシー)
- ジョン・F・ケネディ高校の副校長。生真面目で規律を重んじるタイプ。ユニークなホランドと度々意見がぶつかる。
- コルトレーン・ホランド(成年:アンソニー・ナタール / 少年:ジョセフ・アンダーソン / 幼年:ニコラス・ジョン・レナー)
- ホランド家の一人息子。通称コール。先天的に聴覚障がいがある。成長するにつれて、音楽を理解したいと思う反面、父とのすれ違いに葛藤する。
映画『陽のあたる教室』のネタバレあらすじ(起承転結)
映画『陽のあたる教室』のあらすじ【起】
1965年、アメリカのジョン・F・ケネディ高校。ホランドの教職初日はまずまずだった。生徒たちは授業にこそ出席するものの、参加意欲に欠けていた。オーケストラの練習でも、不揃いな演奏でホランドのストレスは溜まる。
ホランドの安らぎは、愛妻アイリスと過ごす時間と合間の作曲作業だ。教職は4年間限定で、作曲家として成功すれば即座に辞職する予定だった。
ホランドが教職にも慣れた頃。3年生のガートルード・クランクはクラリネット奏者だが、オーケストラで度々ミスを連発していた。見かねたホランドは、毎日放課後に一対一でガートルードを指導する。エリート一家に生まれた彼女は、自分だけ平凡なことにコンプレックスを持っていた。根気よく練習を続けるが、クセはなかなか改善されず、ガートルードは自信を失くす。
アイリスは妊娠を打ち明けるが、ホランドのクールな反応に傷つく。けれど、それはホランドが疲弊していたからで、彼は本心では喜んでいた。夫妻は新しい命に心を躍らせた。
クラリネットを諦めたガートルードに、ホランドは、楽譜を見せずに演奏させる。その間、自分の好きな部分を思い浮かべるよう言うと、ガートルードは難所をすんなりクリアした。卒業式での演奏会、ガートルードは晴れ晴れした表情でクラリネットを奏でていた。
映画『陽のあたる教室』のあらすじ【承】
次の夏、ホランド家は一戸建てに引っ越していた。アイリスは男の子を出産し、コルトレーン(以下コール)と名付ける。
ウォルターズ副校長はホランドの自由な音楽の教育方針に異論を唱える。ジェイコブ校長が仲介したことでその場は収まる。結果「あらゆる音楽を教える」方針に則って、ホランドはマーチングバンドを結成するよう指示される。
実際、バンドの指導(特に行進)は易しくはなかった。ホランドは体育科のマイスターに協力を依頼する。マイスターは行進指導を助ける代わりに、一人の男子生徒をバンドに加入させることを希望した。レスリング部エースのルー・ラスは、学業不振で落第の寸前だった。音楽の単位を履修することで退学を免れるのだという。だが、ルーは楽器はおろか、楽譜すら読めない“音楽素人”だった。
ホランドは、最初こそ素人の生徒の受入に消極的だった。けれどもルー本人と対面し、バンドに参加させる。ルーはドラム担当となり、努力するが基本すら習得できない。ホランドはルーの上達を見込めなかった。しかし、マイスターからルーはレスリング以外特技がないことを聞くと、個別の徹底指導に踏み切る。特訓を重ね、ルーは目覚ましい上達を遂げる。
本番のフェスティバル。ラス夫妻やアイリスたちが見守る中、ルーは意気揚々とビートを刻んだ。お祭り騒ぎの中、パトロール車のけたたましいサイレンが鳴り響く。アイリスは眠る息子を心配する。誰もが耳を塞いでいたが、コールは起きなかった。
映画『陽のあたる教室』のあらすじ【転】
帰宅したホランドにアイリスは、コールに難聴の可能性があることを伝える。ホランドは愕然とする。以来夫妻の間に溝ができ、コールの教育やコミュニケーションをめぐって衝突が絶えなくなる。
授業では、優秀だがひねくれ者のスタドラ―が悩みの種だった。そこに教え子の訃報が届く。ドラムを教えたルー・ラスが出征先で戦死したのだ。ホランドは思うところがあり、スタドラーを伴って葬儀に参列する。かつて、瞳を輝かせて音楽に親しんだ生徒は、沈黙の中に横たわっていた。
ホランドはミュージカルを計画していた。新校長のウォルターズは、現在の運営費では負担できないと却下する。しかし、フットボール部が舞台に加わることになると計画は承認された。オーディションでは、美声の持ち主ロウィーナ・モーガンがヒロインに選ばれる。
ホランドはロウィーナの歌唱力を磨くため、個人指導に当たる。妻や息子と不和なこともあり、美しいロウィーナと急接近する。ロウィーナの夢は歌手だが、家業の手伝いがあるために悩んでいた。ホランドは夢を大事にしろ、とロウィーナを激励する。
ミュージカルは大盛況に終わる。ロウィーナはこのままNYへ発つことを決め、ホランドに一緒に来てくれと願う。彼女に惹かれていたホランドは揺れるが、家族への愛を再認識する。そして、一人旅立つロウィーナを見送った。
映画『陽のあたる教室』の結末・ラスト(ネタバレ)
1980年。ホランドはジョン・レノンの死に心を痛めていた。それを茶化したコールに激昂するが、コールも悲しんでいることや、本当は音楽に触れたいことを知る。ホランドは息子との長年の空白を埋めようと決意する。
ホランドは聴覚障がいの子どものために、特別な工夫が施されたコンサートを開く。演奏の後、ホランドは手話をしながら息子に向けて『Beautiful Boy』を歌った。この瞬間、ホランド親子のわだかまりは温かく解けていった。
1995年。ホランドは教師生活30年を迎える。財政難の高校は経営費削減のため、芸術系授業の廃止を決める。ホランドは、子どもの創造性が奪われると、廃止の取りやめを委員会に求める。だが、訴えは聞き入れられなかった。帰郷中のコールやアイリスと、ホランドは学校を去る準備をする。
去り際、講堂から賑やかな音がした。ホランドたちが入ってみると、送別会が開かれていた。学校をあげてホランドの引退を祝う計画が密かにあったのだ。出席者にはかつての教え子たちも揃っていた。感極まるホランドに、生徒たちはホランドが作った交響曲を演奏すると言う。目に涙をにじませながら、ホランドは最後の指揮を執るのだった。
映画『陽のあたる教室』の感想・評価・レビュー(ネタバレ)
素直に感動する素晴らしい作品である。1人の父親として、そして1人の音楽家としての生き様を描いている。終盤にかけて物語は盛り上がっていき、最後に主人公の生き様が現れている。
例えば将来について思い悩んでいる若者や、今の仕事に疑問を持っている人には響く作品だろう。人生について深く考えさせられる。結果的に主人公は本当にやりたかったことができなかった。しかしそれも彼が選んだことで、やりたいことよりももっと大事なことを見つけたのだ。観る人はそれぞれ自分の人生と照らし合わせてしまうだろう。(男性 20代)
音楽の力と人の成長、温かな涙に溢れる名作でした。特に最終学年の演奏会で、かつて反抗的だった生徒たちが心をひとつにして演奏する姿には、胸が熱くなりました。ミスター・ホランドのあきらめない姿勢が周囲を変えていく過程が丁寧で、教師の“本質”を見せられた気がします。最後に彼が娘への手紙に綴った言葉、「わたしの遺産はあなたの中にある」は心に深く残りました。(20代 男性)
娘を持つ母親として胸に迫る物語でした。ミスター・ホランドは、最初は音楽家としての夢を教師に譲ったように見えるけれど、生徒たちへの影響こそが彼の真の“作品”だった。末期がんでその生徒たちと別れるシーンは、涙を堪えられませんでした。人生の仕事とは何か、教師の存在意義とは何かを問い直される映画です。(40代 女性)
教職に憧れる学生として、理想の教師像を見た気がします。ミスター・ホランドは教育現場の厳しさにぶつかりながらも、生徒一人ひとりの個性を大切にし、音楽を通して彼らを導きます。特に聴覚障がいの生徒とコミュニケーションを模索する場面には感銘を受けました。自分もいつか、こんな教師になりたいと思える映画です。(20代 女性)
自分も教師として働いているので、他人事とは思えませんでした。予算不足や保護者、管理職との折衝など、教育現場の現実を描きながらも、ミスター・ホランドは“生きた教育”を貫く。その信念が最後には学校運営を支える象徴になったシーンは感動的でした。理想と現実のせめぎ合いを描いた素晴らしい作品です。(50代 男性)
音楽好きの一人として心が震えました。映画中の演奏場面がすべて美しく、特に最後の演奏会でミスター・ホランドの妻が号泣する姿にはこちらも泣かされました。彼が生徒の“心”に触れ、彼らにとってのヒーローになる過程は音楽の普遍的な力を感じさせます。教育とは技術ではなく、魂を伝えることなんだと教えられました。(30代 女性)
父親が教師だったので、この映画は自分の家族史とも重なりました。父も生徒に慕われていたことを思い出し、なんだか誇らしくなった。ミスター・ホランドの人生の集大成は、音楽ではなく“人とのつながり”だったことが、ラストで鮮やかに描かれていて胸が熱くなりました。温かくて深い映画です。(60代 男性)
人生に迷う若者にこそ観てほしい映画です。夢を追う一方で現実に妥協してしまうミスター・ホランドの姿は、多くの社会人の鏡のようでした。しかし、彼が最後に見つけたのは“目の前の人を変える”という使命だった。普通の日常の積み重ねが人生を豊かにすることを教えてくれる、優しくて強い映画です。(30代 男性)
初見では父と教師という立場に引いてしまった自分ですが、見返すたびに泣けるようになりました。こどもとの時間を犠牲にしてしまう屈折した愛情の表現や、別れのシーンでの“音楽が心に響く力”に改めて圧倒されました。映画を観終わったあと、自然と「ありがとう」と呟いてました。(20代 女性)
子どもの頃に観た時はただの感動作だと思っていたけれど、大人になってから見直すと、芸術と教育について深く考えさせられます。音楽への情熱が消えていく過程と、それでも生徒と繋がろうと奮闘する教師の孤独と誇り。ラストの講演で生徒たちから感謝の言葉のシャワーを浴びる姿は、人生の“確かな成果”を象徴しているようでした。(50代 女性)
映画『陽のあたる教室』を見た人におすすめの映画5選
グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち
この映画を一言で表すと?
天才と教師の心が触れ合う、魂をゆさぶるヒューマンドラマ。
どんな話?
マサチューセッツ工科大学の清掃員として働く青年ウィルは、実は数学の天才。問題を抱える彼を見つけた心理学者ショーンは、彼の心を開くために奮闘する。互いの傷を乗り越えて成長していく姿が感動的な名作です。
ここがおすすめ!
「陽のあたる教室」が教師の献身を描いた作品なら、こちらは生徒の再生に焦点を当てた作品。ロビン・ウィリアムズの深みある演技と、ウィルの抱える孤独と才能の葛藤が胸に刺さります。涙なしには見られない感動作。
スクール・オブ・ロック
この映画を一言で表すと?
音楽が子どもたちの心を変えていく、痛快ロック・エンタメ。
どんな話?
落ちこぼれバンドマンのデューイが、ひょんなことから名門小学校の代用教員に。厳格な学校にロック魂を持ち込み、子どもたちを音楽の力で変えていく物語。爆笑と感動が詰まったエネルギッシュな1本です。
ここがおすすめ!
音楽と教育の融合という意味で『陽のあたる教室』と共通点があります。デューイの破天荒な授業風景と、生徒たちの成長する姿は元気をもらえる内容です。家族で安心して観られるエンタメ要素も満載。
今を生きる
この映画を一言で表すと?
自由な精神を教える教師と生徒たちの、切なくも美しい青春物語。
どんな話?
名門男子校に赴任してきた型破りな教師キーティング。彼の独自の指導が、生徒たちに「自分の人生を生きる」という価値観を芽生えさせていく。自由と抑圧、夢と現実が交錯する感動の名作です。
ここがおすすめ!
教師の影響が生徒の人生をどう変えるのか。『陽のあたる教室』と同じテーマを持ちながら、より劇的で衝撃的な展開が描かれます。青春時代に一度は観ておきたい、人生観が揺さぶられる作品です。
愛と追憶の日々
この映画を一言で表すと?
親子の葛藤と愛を繊細に描いた、時間を越えて響くドラマ。
どんな話?
強い個性を持つ母親と、自由に生きようとする娘。二人のすれ違いや愛憎、そして別れを描いた家族ドラマ。ユーモアと切なさが共存し、観終わったあとに深い余韻が残る物語です。
ここがおすすめ!
人生の意味や家族とのつながりを描く点で『陽のあたる教室』と共通しています。シャーリー・マクレーンとデブラ・ウィンガーの圧巻の演技が光る、アカデミー賞に輝いた傑作ヒューマンドラマです。
コーラス
この映画を一言で表すと?
歌声が心を照らす、フランス発の感動系音楽映画。
どんな話?
問題児ばかりが集まる寄宿学校にやって来た音楽教師クレマン。彼は合唱を通じて、生徒たちの心に変化を与えていく。希望と優しさに満ちた、美しいハーモニーが響く感動作です。
ここがおすすめ!
音楽教育をテーマにした感動作として、『陽のあたる教室』と最も近い雰囲気を持つ作品。少年たちの純粋な歌声と、それを導く教師の姿に涙がこぼれます。音楽と愛に満ちた、心に残る映画です。

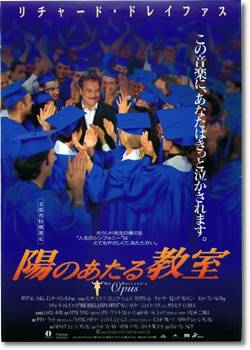


みんなの感想・レビュー