第二次世界大戦で敗戦国となった日本は、“二度と戦争はしません”と世界に約束し、この70年間はその約束を守ってきた。しかし地球上から戦火が消えることはなく、今この瞬間もどこかで愚かな殺し合いが続いている。平和な環境で暮らしている私たちは、映画から戦争の不毛さや狂気を学び、平和を維持する努力を続けるべきだろう。
戦争映画のおすすめランキング10選
第1位 地獄の黙示録 特別完全版
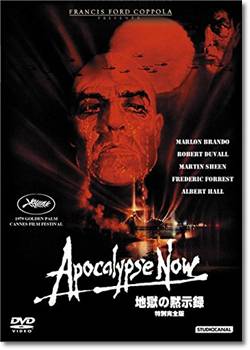
ベトナム戦争後期、アメリカ軍空挺部隊のウィラード大尉は、殺人罪により脱走兵となったカーツ大佐を極秘で暗殺するため、水路でカンボジアとの国境付近を目指す。
いくら正義を主張しても、戦争というのは結局のところ殺し合いだ。敵ならば、何人殺しても裁かれないのが戦争であり、そもそもの根底が狂っている。情け容赦なく人を殺せるような悪魔にならなければ、戦場では生き残れない。戦場というのは、地上の地獄であることは間違いない。
多くの戦争映画は、“それでも人間だから”というヒューマニズムを描こうとする。だから戦争映画には泣ける映画が多い。しかしこの「地獄の黙示録」に、ヒューマニズムなど存在しない。全編を通して唖然とするような狂気の世界が描かれる。
“サーフィンがやりたい”と言い出し、部下に“あの辺はベトコンの拠点があるので危険です”と止められると、“潰してしまえばいい”と言い放ち、本当に敵の基地を派手に奇襲するキルゴア中佐。ロバート・デュバルの演じるキルゴア中佐が「ワルキューレの騎行」を爆音で鳴らしながら空軍ヘリで敵地へ乗り込むシーンは、映画史に残る名シーンだ。そのイカれ具合が半端ではない。
マーロン・ブランドが演じるカーツ大佐の王国に至っては、もはやホラーの世界。あちこちに無数の死体が転がっているが、誰もそれに反応しない。仏教の「地獄絵」を見たことがある人は、あの世界観を想像してもらうと話が早い。この地獄の主であるカーツ大佐は、人間を感じさせない。マーロン・ブランドが漂わせる不気味な静けさの中には、圧倒的な狂気と破滅が存在する。
フランシス・フォード・コッポラ監督は、生ぬるいヒューマニズムを完全に排除し、“戦争なんてこんなものだろう”と言い切っている。この作品はコッポラ監督の綴った黙示録、つまり終末論なのだ。
詳細 地獄の黙示録 特別完全版
第2位 大脱走
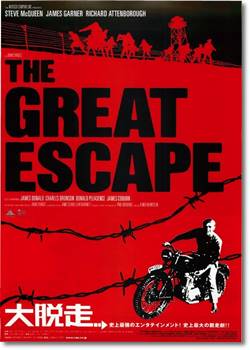
ドイツ軍の捕虜収容所に収容された連合軍の捕虜たちは、総勢250名で脱走するという壮大な脱走計画を立てる。第二次世界大戦時、オーストラリア空軍兵士だったポール・ブリックヒルの実話に基づく物語。
“ドイツの収容所”というキーワードから、ナチスの強制収容所を連想する人が多いと思うが、本作の舞台は捕虜収容所なので、全く趣が異なる。捕虜というのは保護される立場にあるので、収容所内において一定の自由が許される。脱走を図った場合でも、軍人であることが証明されれば、敵側は捕虜を勝手に処刑できない。そのため、捕虜となった軍人は、任務のような感覚で脱走を繰り返す。
頻繁に脱走が繰り返されるため、ドイツ軍は脱走の常連を一箇所に集め、厳重に管理しようとする。しかし脱走のプロが集まれば、当然脱走を企てる。前半部分は、このプロ集団が緻密な計画を立て、着々と準備を進めていく様子が描かれる。この辺りは秀悦な作りの犯罪映画を見ているような楽しさがある。
ところが、脱走が決行され、各自がバラバラに逃亡する後半部分は、主にゲシュタポ(ドイツの秘密警察)との戦いになっていくので、空気が一気にはりつめる。物語におおらかさがなくなり、手に汗握る展開が続く。スティーブ・マックイーンの演じるヒルツが、バイクで疾走するアクションシーンだけは、一種の爽快さがあるのだが、狭い街中で何度もゲシュタポに遭遇するバートレットの逃亡劇は、心理的に追いつめられていくサスペンス映画のような怖さがある。
戦場は一切描かれず、娯楽映画のように面白いというのが、この作品の最大の特徴でもある。戦争の不条理さはしっかり描かれているが、脚本、演出、キャスティング、音楽、撮影など、あらゆる点で映画としての完成度が非常に高い名作なので、戦争映画が苦手な人にもおすすめできる。
詳細 大脱走
第3位 二十四の瞳(1954)

瀬戸内海の小豆島にある岬の分教場で、新米教師となった大石先生は12名の新入生たちを受け持つ。大石先生は、子供たちの幸せを祈り続けていたが、貧困や戦争という残酷な現実が、可愛い教え子たちを奪っていく。
この作品は18年間の時間経過を描いているので、小学一年生だった子供たちは、当然大人へと成長していく。子供の成長を自然な状態で見せるため、6歳前後の分校時代と12歳前後の本校時代を演じる2名の子役は、ほとんどが実の兄弟だ。そのため、子供たちの成長具合に違和感がない。さらに、子供たちの素朴な表情があまりにも自然で、とにかく可愛い。気がついたら“頼むから元気に成長してくれよ!”と本気で願っているし、“この子たちに悲しいことが起こりませんように”と祈っている。これはまさに大石先生の気持ちそのものだろう。
観客を自然に感情移入させてしまう木下惠介監督の演出は素晴らしい。“大石先生と子供たちを見ている”のと“大石先生の気持ちで子供たちを見つめている”のでは、映画から受ける印象が全く異なる。大石先生の視点で子供たちを見ていると、彼らを不幸にしていく不条理な現実への怒りが込み上げてくる。教師を辞めてしまった大石先生の選択にも矛盾を感じない。
物語の後半で、大石先生は泣き続けている。前半部分では、子供たちとあんなに楽しそうに笑っていた大石先生が、事あるごとに涙を流す。しかしそれはお涙頂戴の安っぽい演出ではなく、説得力のある必然の涙だ。あの子たちのまっすぐな「二十四の瞳」を思い出すと、自然と涙がこぼれてしまうのが、当たり前の人間の感情というものだろう。
鑑賞後は、子供たちの歌う「七つの子」や「仰げば尊し」といった美しい唱歌の調べが耳に残り、長い余韻が続く。日本人なら一度は見ておきたい、まぎれもない名作映画だ。
詳細 二十四の瞳(1954)
第4位 ノー・マンズ・ランド
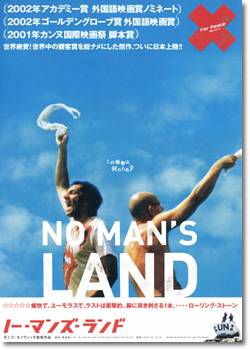
1992年、東欧のボスニア・ヘルツェゴビナでボスニア軍とセルビア軍が戦うボスニア紛争が勃発する。この作品は、ボスニア軍兵士とセルビア軍兵士が、同じ塹壕の中に取り残され、生き残る道を模索していく物語だ。塹壕の中にはボスニア軍兵士のチキとツェラ、セルビ軍兵士のニノという3人の兵士がいる。チキとニノは自由に動けるが、ツェラは意識を失っている間にジャンプ式の地雷の上に寝かされてしまい、全く身動きが取れない状態となっている。少しでも動けば地雷が爆発し、ツェラは吹っ飛ばされてしまう。
3人とも生き残るためには、チキとニノが協力してこの状況を両軍に伝え、戦闘を一時中断した上で、ツェラの下の地雷を処理してもらう必要がある。しかし、国連防護軍上層部の対応は冷酷で、彼らを救出することよりも、マスコミ対策にばかり気を取られている。マスコミもまた、国連を非難してチキたちを援護するようなふりをしているが、結局のところ面白いスクープを狙うのが目的だ。この作品は、傍観者たちの無責任さを、痛烈に非難している。
それと同時に、塹壕内での3人のやり取りから、戦争の問題点や矛盾点が浮き彫りになっていく。戦争に“正しい側”など存在しない。より強い武器を持ち、相手をぶちのめした側が、根拠のない正義を肯定する権利を持つ。ただそれだけのことなのだ。
この作品はとにかく脚本と演出が秀悦で、数多い戦争映画の中でも異色の存在感を放っている。作品の規模は小さいが、胸に突き刺さってくるような鋭さを持っており、多くの映画祭で観客賞を受賞していることもうなずける。あまりに無情な結末には、呆然と立ちすくむしかない。
詳細 ノー・マンズ・ランド
第5位 戦場のピアニスト

第二次世界大戦時、ワルシャワでピアニストをしていたユダヤ系ポーランド人のシュピルマンは、ナチスドイツのポーランド侵攻により、ワルシャワの強制収容所に送られる。紆余曲折を経て、とある廃墟に行き着いたシュピルマンは、ドイツ軍将校ホーゼンフェルトと出会い、ピアノを披露することになる。
「チャイナタウン」(74)で知られるポーランドの巨匠ロマン・ポランスキー監督は、この作品で初めてアカデミー賞監督賞を受賞した。1962年に「水の中のナイフ」で長編監督デビューをしてから、約40年間で16作品を作り、17作目にあたるこの「戦場のピアニスト」(02)で、自身の底力を世界中に見せつけた。そういう意味でも、この作品がポランスキー監督の代表作と言って差し支えないだろう。
物語は、ずっと重苦しく暗い。主人公のシュピルマンを演じたエイドリアン・ブロディの役作りが素晴らしく(この役でエイドリアン・ブロディは29歳にしてオスカーを受賞)彼の悲痛な表情や、日に日にやせ細っていく姿を見ているだけで、胃がキリキリと痛む。しかし、この映画の感想を一言で述べよと言われると、“美しい映画”と答えてしまう人が多いのではないだろうか。
この映画の美しさは、ぼんやりと輝く月明かりのように幻想的だ。作中に流れるピアノの音色は、あまりに物悲しく、そして美しい。人間は美しい芸術を生み出す一方で、戦争という残虐な破壊行為を繰り返す矛盾に満ちた生き物なのだ。その矛盾は、この作品が残酷な戦争を描いていながら非常に美しいという矛盾と重なる。
詳細 戦場のピアニスト
第6位 あの日の声を探して

チェチェン紛争によって侵攻してきたロシア兵に両親を殺され、まだ赤ちゃんの弟とともに故郷の村を追われた少年ハジ。彼はショックで言葉を失い、EU人権委員会職員のキャロルに保護される。キャロルは何も話さないハジを持て余しつつも、自分に足りなかったものに気づいていく。一方、ハジの姉のライッサは、戦火の中で生き別れた弟を探していた。
監督のミシェル・アザナヴィシウスは、「アーティスト」(11)でアカデミー賞監督賞を受賞(その他4部門受賞)して本作の資金集めに成功し、長年温めてきたこの企画を映像化することができた。似たような作品で連続ヒットを狙うのではなく、本当に作りたい作品に挑んでいくという姿勢は高く評価したい。
この作品の冒頭部分は、誰かが撮影しているハンディカメラの映像で始まる。その映像があまりにリアルなので、“あれ?これってまさかドキュメンタリー!?”と、本気で焦る。そして撮影用カメラの映像に切り替わってからも、ハジを演じているアブドゥル君が本気でロシア兵に怯えているように見えるので、“これってフィクションですよね!?”と、不安のあまり誰かに問いかけたくなる。それほど真に迫った映像が続くのだ。ハジが言葉を発しないということも、リアルさに拍車をかけている。
物語の主軸はハジとキャロルの交流にあるが、ハジを探す姉のライッサの物語と、そことは全く関係のないコーリャというロシアの若者の物語が同時進行していく。ロシア軍に強制入隊させられたコーリャの物語も強烈で、暴力によって人間はどのように変化していくのかが、情け容赦なく描かれている。そして、バラバラだった物語がシンクロしていき、最終的には一本の線になる。人間の善意と残酷性が入り混じったそれぞれの結末が、なんとも言えない余韻を残す。
戦争映画ではあるが、ミシェル・アザナヴィシウス監督の巧みな構成力と演出のうまさが際立つ秀悦なヒューマンドラマとしておすすめしたい。そしてハジを演じたアブドゥル君は天才だ。
詳細 あの日の声を探して
第7位 プラトーン

自ら志願してベトナムの地へ降り立った青年クリスは、想像を絶する過酷な現実を目の当たりにして、戦争の意味や自分がどう生きるべきかを見つめ直していく。
1986年に公開されたこの作品は、第59回アカデミー賞で、作品賞、監督賞、編集賞、録音賞の4部門を受賞した。
監督・脚本を務めたオリバー・ストーンは、自分自身がベトナム戦争の帰還兵であり、実体験に基づいてこの作品を作っている。そのため、アメリカ映画でありながら、アメリカ兵がベトナムの人々に対していかに残酷で非人道的であったかも、非常にリアルに描いている。ベトナムの村で、無抵抗な村人がアメリカ兵に虐待の末、殺害されるシーンは、吐き気をもよおすような残酷さだ。
さらに、アメリカ軍内部での内輪揉めや兵士の薬物依存などの現実も詳細に描かれており、前線の戦地がいかに狂気じみた世界であるかが、否応なく伝わってくる。先に紹介した「地獄の黙示録」ほど強烈ではないが、戦争の狂気を知っておきたいという人は、この作品を見るといい。“一体何のために人間はこんな無意味な殺し合いをするのだろう?”という素朴な疑問が湧いてくる。
詳細 プラトーン
第8位 ディア・ハンター

ベトナムの戦地へ徴兵されることになった親友のマイケルとニックは、ベトコンの捕虜となり過酷なロシアン・ルーレットを体験する。その後、アメリカへ帰還したマイケルは、ベトナムで生き別れたニックが、サイゴンにいると知る。マイケルは危険を冒してニックを迎えにいくが、2年ぶりに再会したニックは、別人のようになっていた。
強靭な精神を持つマイケルを演じるのはロバート・デ・ニーロで、繊細で優しいニックはクリストファー・ウォーケンが演じている。後半部分に登場するクリストファー・ウォーケンは、前半とは別人のように病的な姿になっており、過酷な体験と薬物により、ニックが廃人になってしまったことが一目でわかる。この徹底的な役作りで、クリストファー・ウォーケンはアカデミー賞助演男優賞賞を受賞した。本作はアカデミー賞で9部門にノミネートされ、5部門でオスカー像を手にしている。
メリル・ストリープは本作がまだ2本目の映画出演であり、マイケルとニックに愛されるリンダを演じてアカデミー賞助演女優賞にノミネートされ、有名女優の仲間入りを果たした。さらに、当時メリルの婚約者だったジョン・カザールが、マイケルたちの友人スタンリー役で出演している。彼はこの時すでに末期ガンに冒されており、本作が事実上の遺作となってしまった。「ゴッドファーザー」(72)のフレド役や、「狼たちの午後」(75)でのサル役などで存在感を示し、まさにこれからという時に亡くなってしまったジョン・カザールが、本作でも病を感じさせない名演技を見せている。
ベトナム戦争を題材とした戦争映画なら、「地獄の黙示録」「プラトーン」と並んで、この「ディア・ハンター」は絶対に押さえておきたい作品である。
詳細 ディア・ハンター
第9位 ジョニーは戦場へ行った
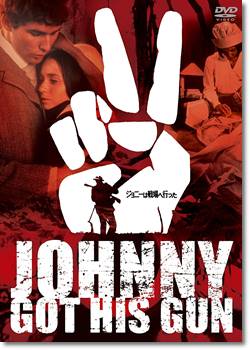
第一次世界対戦で徴兵されたアメリカ軍兵士のジョーは、戦場で爆撃を受け、目と耳と鼻と口を失う。さらに壊死した両手足も切断され、生きる肉塊として陸軍の研究材料にされてしまう。医師はジョーに意識がないものと思い込んでいたが、ジョーは意識を取り戻し、心の中で“助けてくれ!”と叫び続けていた。
原作の「ジョニーは銃を取った」は1939年に発表された反戦小説で、作者のダルトン・トランボは、小説発表から32年後の1971年に、自ら監督・脚本を務めて、この「ジョニーは戦場へ行った」を製作した。赤狩りの標的にされ、ハリウッドから追放されたトランボは、生活費のために偽名で脚本の執筆は続けていたが、表舞台での活動はできずにいた。そのため、この作品が唯一の監督作である。そういう背景もあって、この作品にはトランボの戦争に対する憎しみが凝縮されている。
物語は、生きる肉塊となったジョーの心の声や空想世界、さらに彼を見つめる人々の視点で構成されている。想像を絶する苦しみの中で、ジョーは必死で自分が生きる意味を考える。彼は最終的に“自分の姿を多くの人に見てもらいたい”という結論に達する。自分の姿を見てもらうことで、戦争の残酷さを訴えようとした。しかしその望みさえ聞き入れてもらえない。唯一の伝達手段であるモールス信号で“SOS”を発し続けるジョーの姿を通して、戦争の罪は人間の尊厳を奪うことにあるのだと、トランボは伝えたかったのだろう。
詳細 ジョニーは戦場へ行った
第10位 ビルマの竪琴(1956)

ビルマの戦地で終戦を迎えた水島上等兵は、雨露にさらされ、野ざらしになっている同胞たちの屍を見て、この地に残って彼らの遺体を埋葬する決意をする。しかし、そこには苦しい葛藤があった。
原作は竹山道雄の同名児童文学であり、それを市川崑監督が1956年に映像化した。脚本は、公私ともに市川崑監督のパートナーだった和田夏十。市川崑監督は、この作品を1985年にセルフリメイクしており、その際も和田夏十が脚本を担当している。
水島上等兵が所属する部隊の井上隊長は、音楽学校を出ており、この部隊はことあるごとに歌を歌う。その時伴奏役を勤めるのが現地の竪琴を弾ける水島上等兵で、この設定が物語の端々で効いてくる。さらに現地の物売りの婆さんと言葉を覚える兄弟のインコが重要な役目を果たしており、小道具の使い方が非常にうまい作品だと言える。
“オーイ、ミズシマ、イッショニ、ニッポンヘカエロウ”というインコのセリフは有名であり、物語を締めるのも、“アア、ヤッパリジブンハ、カエルワケニハイカナイ”というもう一羽のインコのセリフだ。インコがその言葉を発することによって、水島上等兵が“ああ、やっぱり自分は、帰るわけにはいかない”と繰り返し呟き、この地にとどまるべきか、帰国するべきか、つらい葛藤を続けていたことがよくわかる。インコにそのセリフをリピートさせることで、水島上等兵の心情が、より効果的に伝わってくる。
竪琴が奏でる「埴生の宿」や「仰げば尊し」の美しいメロディは、文句なしに涙腺を刺激する。しかし、作品全体から受ける印象はジメジメと暗いものでは決してない。北林谷栄の演じる物売りの老婆が奇妙な関西弁を話す演出など、いかにも市川崑監督らしくて気持ちが和む。北林谷栄の物売りの老婆を市川監督は気に入っていたらしく、彼女だけが同じ役で、56年版と85年版の両方にキャスティングされている。
水島上等兵の選択は確かにつらいが、一方で彼は腐敗した俗世間から解放され、崇高で穏やかな人生を全うするのではないだろうかとも思える。いや、そうであってほしい。
詳細 ビルマの竪琴(1956)

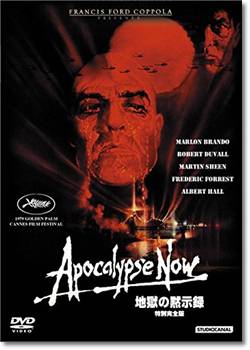


みんなの感想・レビュー